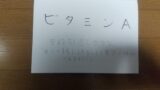みかんとは
みかんとは、ミカン科ミカン属に属する果物(準仁果類)です。旬は一般的に、秋から冬の終わりにかけてという事が多いです。
広い意味で、オレンジやグレープフルーツの仲間で、それらと一まとめにして「柑橘類(かんきつるい)」として扱われます。
簡単な歴史
今の日本において、「みかん」と呼ばれる果物は、厳密には「温州みかん」と分類されます。日本には、唐の時代に伝来したとされる説があります。
農学者田中長三郎の研究により、現在の鹿児島県出水市長島にあった古木から、当地が日本における発祥の地として有力視されています。出水市長島には「温州みかん発祥の地」の石碑が建っています。
ちなみに温州みかんは、欧米では「サツマオレンジ」と呼ばれています。
良品の選び方
※ここに挙げた特徴を持つみかんを選ぶと、良品に出会える可能性が高くなります。
※皮が実から離れてフカフカしてしまっているものは、選ばない方が良い事が多いです。
・ヘタの緑色がみずみずしいもの
・ヘタの軸が細いもの
・平らで皮がなめらかで、色が濃いもの
保存方法
常温保存の場合
ヘタを下にして、ペーパータオルで包んで保存します。
冷蔵の場合
冬場以外は冷蔵した方が良いです。ペーパータオルで包んでポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存します。これで約1週間は保存出来る事が多いです。
冷凍の場合
皮をむかず丸のまま冷凍する場合
水に通して濡れたまま冷凍庫で保存します。これで約2か月保存出来る事もあります。
皮をむく場合
皮をむいて食べやすい大きさに小分けし、ラップで包みます。その後、冷凍用保存袋に入れて冷凍室で保存します。これで約1か月保存出来る事もあります。
栄養素

みかんはビタミンCの補給源になります。また、少量ではありますが、ビタミンAとビタミンB₁を含みます。以下ではそれらの栄養素と、あわせて注目したい成分についてお話しします。
ビタミンC
肌を美しく保つコラーゲンの生成に関わります。そのため、美肌作りに欠かせないビタミンです。抗酸化作用がある事から、ガンや動脈硬化予防などにも力を発揮します。さらに、身体の免疫にも関わり、ビタミンCの適度な摂取は、風邪などの感染症予防にもつながる事があります。
ビタミンA
抗酸化作用があり、ガンや動脈硬化予防などに力を発揮します。また、目や皮膚、粘膜の健康維持にも強く関わります。
以下のリンクで私がビタミンAについて解説しているので、参考にしてくださると嬉しいです。
ビタミンB₁
糖質の代謝に強く関わります。これは、糖質から上手くエネルギーを作れるかどうかに関わると言えます。そのため適度な摂取は疲労を回復し、身体に活力が生まれる事があります。その他、ストレスの軽減にも役立ちます。
その他
みかんに含まれる酸味のもとであるクエン酸は、疲労回復効果があります。そのため、一定程度酸っぱいみかんの方が、実は疲労回復に役立つともいえます。
そしてビタミンPは、毛細血管を強くして、動脈硬化を予防します。白い筋の部分に多いです。
さらに色素成分のβークリプトキサンチンは、β-カロテンよりも抗酸化作用が高く、ガンや動脈硬化予防などに力を発揮する事があります。
みかんと健康
みかんは健康に関して、以下に挙げる事に関して特に役立つ可能性があります。
・がん予防
・風邪や感染症予防
・動脈硬化の予防
・抗ストレス作用
品種
この記事の最初の方でもお話ししましたが、みかんは細かく言うと温州みかんといわれるものに分類され、柑橘類の一種です。
柑橘類―レモンなどの香酸柑橘類も含めるとさらに膨大な数になる―は大変仲間が多く、ここですべての品種を挙げる事は出来ませんが、店頭で売られている色々な柑橘類を購入して、読者の皆様の舌で、ぜひその違いを楽しんでみてください。
みかんゼリー―齋藤瞬のチャレンジクッキング
前置き
この記事の最後に、私が実際にみかんを使った料理を紹介します(実際に私が作って撮影もしています)。
今回は作りやすさを重視するために、みかんの缶詰めを利用しています。
今回作ったのは「みかんゼリー」です。インターネットで、料理研究をされている諸先輩の作り方を学んだところ、案外簡単に作れる事がわかりました(やけどなどには注意が必要ですが)。
美味しいデザートなので、楽しみながら作って行きましょう!
材料(5人前程度)

・みかんの缶詰め・・・1缶
・粉寒天と水・・・粉寒天4gに対して水約500ml
・砂糖・・・50g以上でお好みの量
工程
1.耐熱皿に缶詰めのみかんを入れる
※一皿に入り切らない場合は、何皿かに分ける(私も3皿に分けました)。この時少し缶詰めの液汁を入れても美味しくなります。
2.水を温め沸騰したら、粉寒天を溶かす
3.溶かしたら火を止め少し冷まし、みかんが入った耐熱皿に溶かした粉寒天を投入する
4.さらに粗熱を取り、ある程度冷めたら冷蔵庫で約30分冷やす
※冷たさを楽しみたい場合、1時間以上冷やしても良いです。
5.ゼリー(寒天)が固まったら、完成です!
試食と感想

案外簡単に作れる事は知った後でも、実際に作ってみると「上手く固まるのか」とか「美味しくなるのか」とか、様々な不安がやってきました。
しかし、完成したゼリーは良い色で、しっかりと固まっていました。実際に食べてみると、市販されているゼリーの様には行かなかったものの、美味しく感じる事が出来ました。匂いも甘い匂いがして、食欲が湧いてくるものに出来ました。
補足
実は今回の料理で私は砂糖ではなく、オリゴ糖を使ってみました。何だかヘルシーな気がしたからです(笑)。オリゴ糖の量が足りなかったせいか、思ったより甘さ控えめになりましたが、砂糖以外の甘味料を使ってゼリー作りを楽しむのも、とても良い事だと思います。
みかん以外のフルーツを入れると、さらに美味しくなるだけでなく、目でも楽しめるようになると思われます。
参考文献
・中野瑞樹著 企画・編集株式会社夢の設計社 株式会社河出書房新社発行「中野瑞樹のフルーツおいしい手帳(初版)」2023年7月20日 44~50頁
・青髪のテツ著、ムラセセラマンガ 株式会社Gakken発行「マンガでわかる やさいのトリセツ 野菜のプロが教える選び方・保存法・無駄なくおいしく食べるコツ(初版)」2023年7月11日 229頁
・川端理香監修 株式会社宝島社発行「毎日使える!野菜の教科書」2017年6月2日 142頁
・白鳥早奈英、板木利隆監修 株式会社高橋書店発行「もっとからだにおいしい 野菜の便利帳」2020年7月10日 168~170頁
・吉田企世子監修 株式会社エクスナレッジ発行「春夏秋冬おいしいクスリ 旬の野菜の栄養事典最新版(初版)」2016年5月23日 184、245~264頁